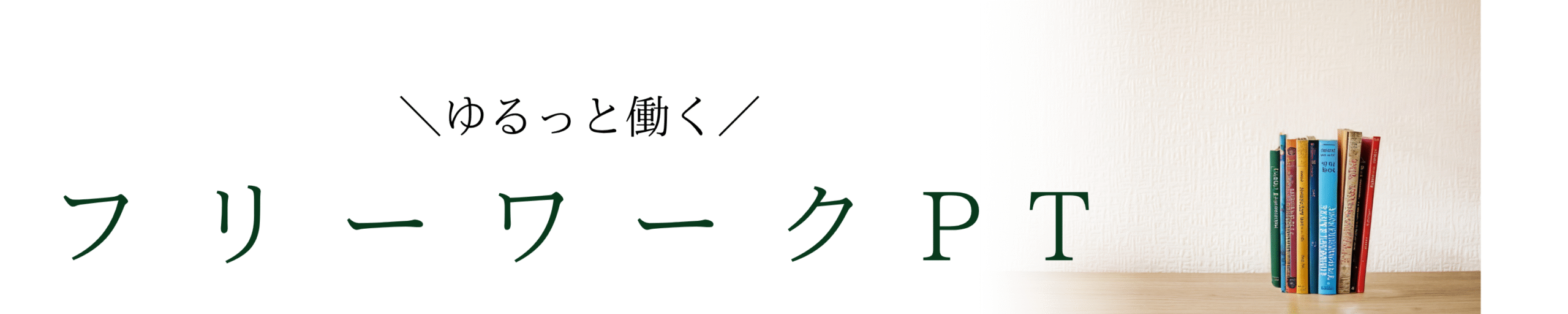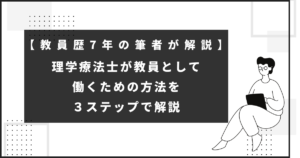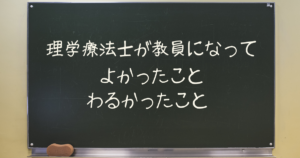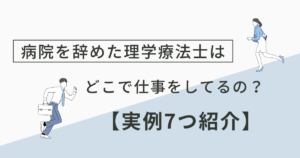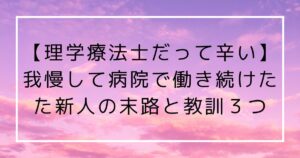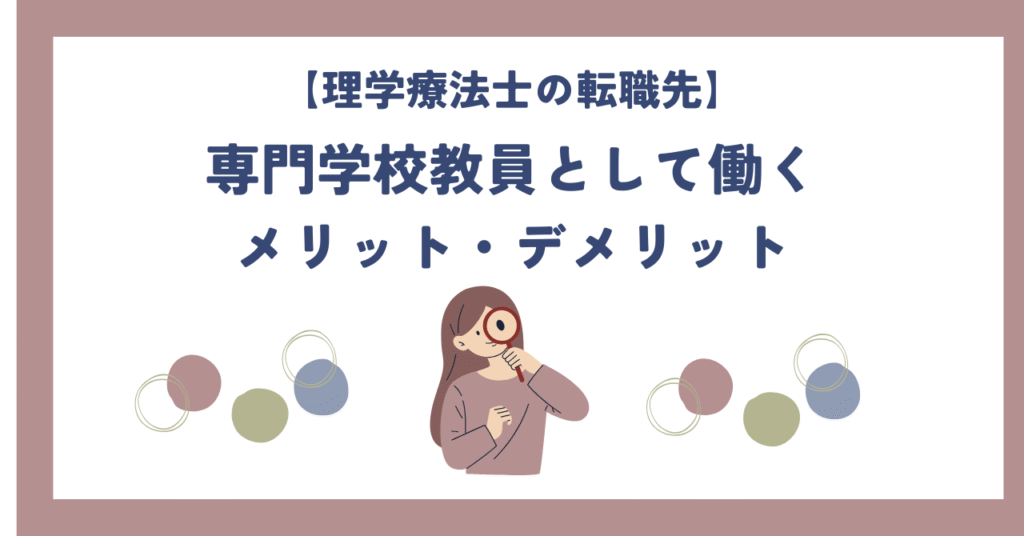
臨床現場を離れた理学療法士の転職先として、よく挙がるのが「専門学校の教員職」です。
「経験を活かして後進を育てたい」「体力的に続ける自信がなくなってきた」など、様々な理由で教員というキャリアに関心を持つ方が増えています。
しかし、教員という仕事には“理想”と“現実”のギャップも存在します。
この記事では、実際に教員として働いた筆者の経験をもとに、専門学校教員のリアルをお伝えします。

- 資格:理学療法士(PT)、介護支援専門員(ケアマネ)
- 病院・施設・在宅リハなど幅広く経験
- 専門学校で理学療法士養成に従事
- 延べ500人以上の学生の就職相談にのる
- 適応障害(うつ状態)をきっかけに働き方を見直す
- 理学療法士・元教員の視点から、コンテンツを発信中
教員になるまでの流れと必要な条件

専門学校の教員になるために、必須の資格は特にありません。
所定の経験年数と養成校教員研修の履修により専任教員として働くことができる学校がほとんどです。
ただし、実際の採用条件としては以下の点が重視されます。
- 臨床経験年数(5年以上が目安。10年以上あればより有利)
- 担当可能な領域が明確(運動器、神経系、小児、内部障害など)
- 教育への意欲と、基本的なPCスキル(パワポ、エクセル等)
求人は、学校法人の公式サイトやPTOTSTワーカー、PTOT人材バンク、レバウェルリハビリなどの転職エージェント経由で出ることもあります。非公開求人も多いため、複数のルートで探すことが重要です。
▶️【無料相談受付中】
教員職に興味がある方は、医療職専門の転職エージェントに相談してみましょう。
👉 PT・OT・ST WORKERで非公開求人をチェックする
👉 PTOT人材バンクで無料相談する
👉レバウェルリハビリで希望条件を伝える
教員になる詳しい条件や、私が教員になるまでの経緯は以下の記事でまとめています。
興味のある方は参考にしてください。
教員の仕事:理想と現実

教員の仕事は、「講義をしていればよい」だけではありません。
実際には以下のような業務が日常的に発生します。
- 授業準備(スライド、資料、実技教材の作成)
- 試験の作成・採点・成績処理
- 担任業務(学生指導、保護者対応)※学校による
- 就職支援・履歴書添削・面接練習
- 会議、学校行事、入学試験、オープンキャンパス対応など
特に新人教員は、講義準備に多くの時間を要します。
休日返上や業務時間外で準備をすることも珍しくなく、働き方としてはむしろ多忙になるケースもあります。
メリット:教員になって良かったこと
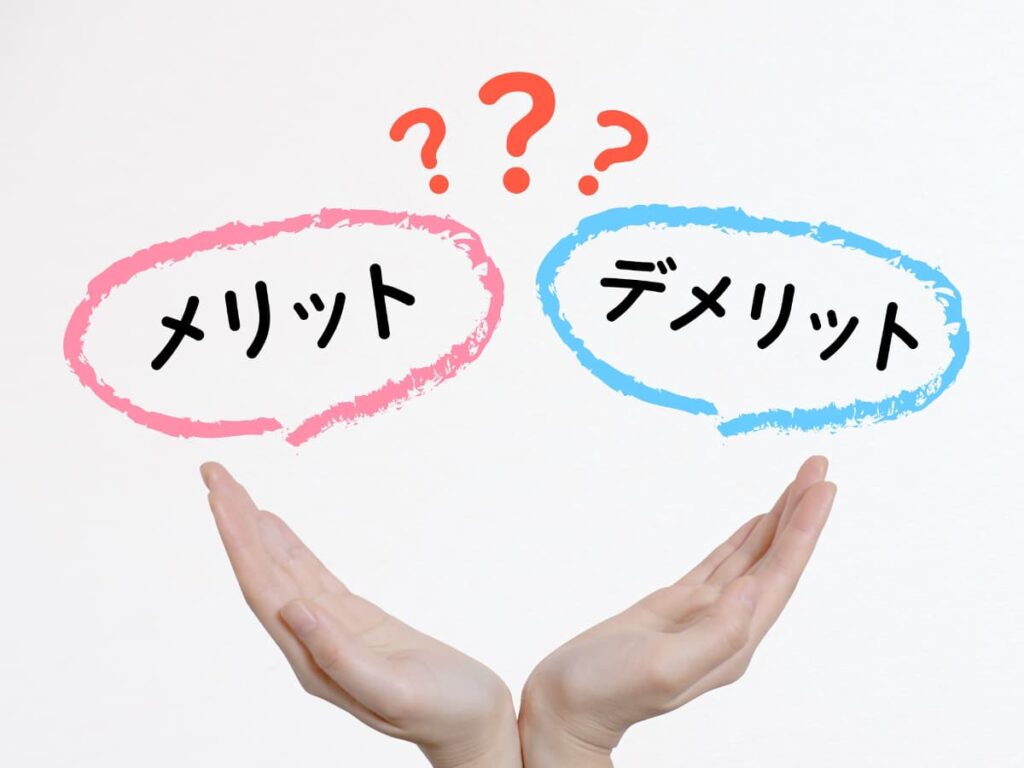
とはいえ、教員ならではのやりがいも確かにあります。
具体的には
- 学生が成長していく姿を見守れる喜び
- 自分の知識を再整理することで、専門性が深まる
- 年間スケジュールがある程度決まっているため、計画的に働ける
- 体力的には臨床より負担が少ない(現場での移動や介助がない)
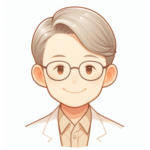 しんた
しんた教育機関ならではの常に“知識を磨ける環境”に身を置ける点も、個人的には魅力的でした。
デメリット:理想と違ったこと
一方で、教員として働く中で感じたギャップもいくつかあります。
- 臨床スキルが高くても「教える力」は別物である
- 学生対応や担任業務で精神的な消耗がある
- 上司・学校運営の方針に従わなければならず、自由度が低い
- 学校によっては教育方針や運営体制が古く、改善しにくい
特に「先生」という立場になると、学生はじめ保護者など、あらゆる視線にさらされる分、プレッシャーも強くなります。
向いている人・向いていない人の特徴
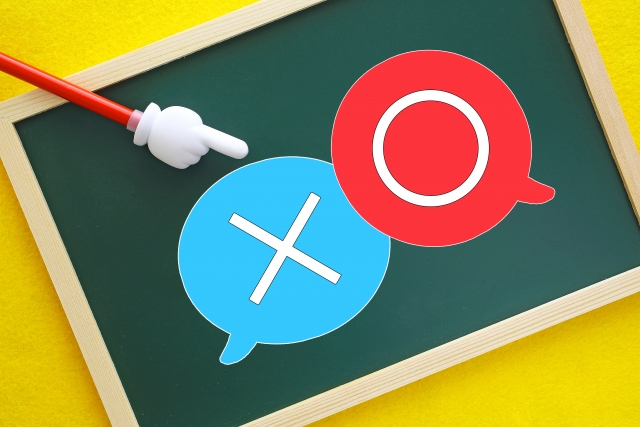
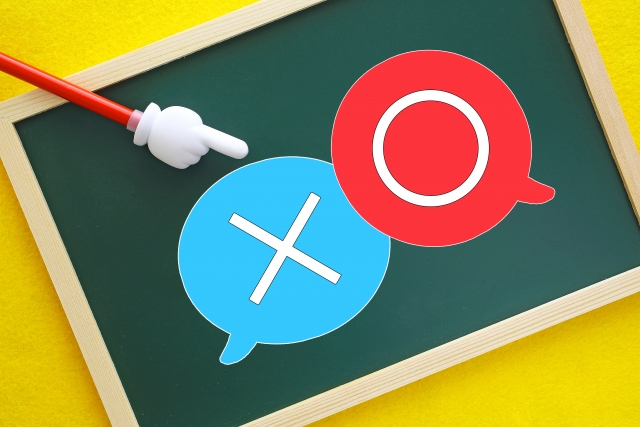
教員職は、向き・不向きがはっきり出る仕事だと働いていて、感じました。
【向いている人】
【向いていない人】
まとめ:教員もまた「一つの選択肢」
理学療法士としてのキャリアに迷ったとき、「教える道」もひとつの有効な選択肢です。
臨床とは違ったやりがいや成長が得られる反面、教育現場ならではの難しさや課題もあります。
大切なのは、「自分の特性と向き・不向きを見極めること」。
そして、「実際に働いている人の声」を参考にしながら、自分に合った環境を探すことです。
転職を検討している方は、まずは医療職専門の転職エージェントで情報を集めることから始めてみてください。
どんな求人があるか、知るだけでも選択肢は広がります。
筆者の教員体験談も、別記事にしています。参考にしてください。