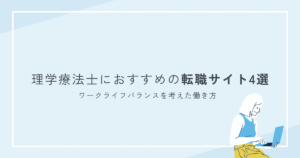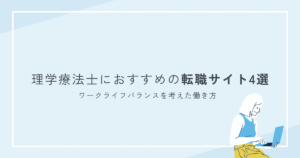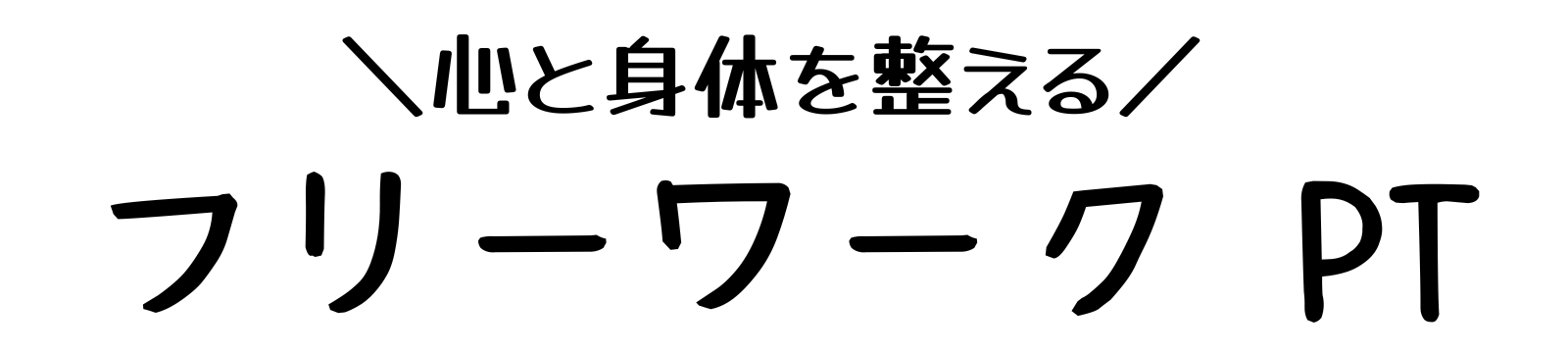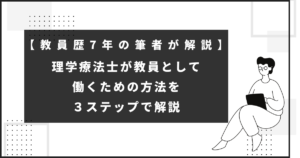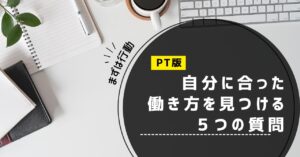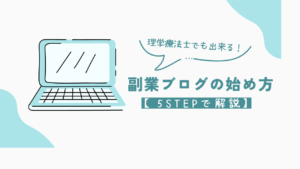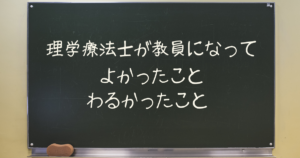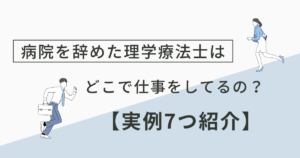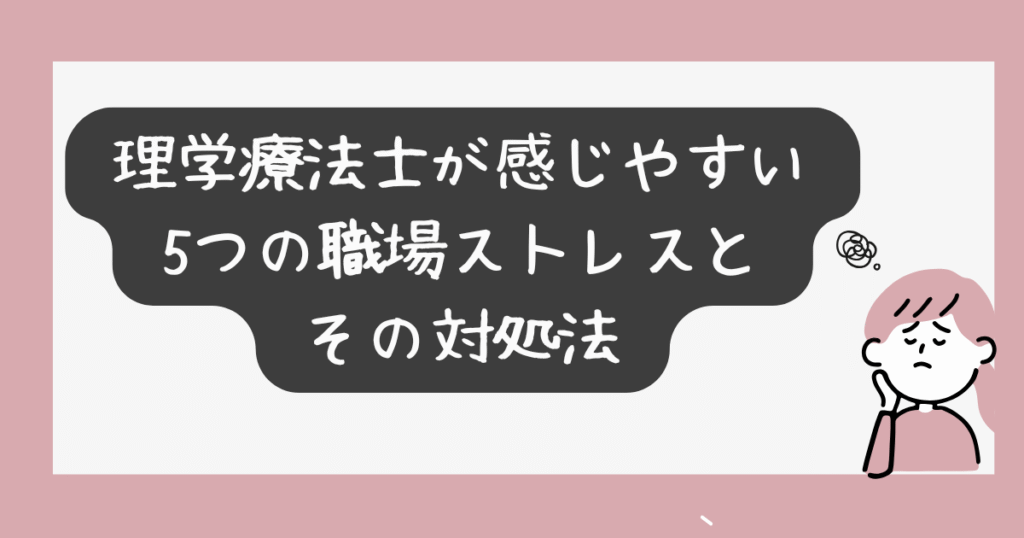
理学療法士は、人の身体機能の回復やQOL(生活の質)向上を支える、非常にやりがいのある仕事です。
しかし、その裏では多くの理学療法士がストレスを抱えているのも事実です。
筆者自身も、臨床経験の中で多くのストレスに悩まされ、どうしたら心の平穏を保てるか、試行錯誤を重ねてきました。
この記事では、理学療法士が抱えやすい職場のストレスを5つに分類し、それぞれに対する実践的な対処法を紹介します。
「なんとなくしんどい」「毎日が苦しい」と感じている方にこそ、読んでいただきたい内容です。

- 資格:理学療法士(PT)、介護支援専門員(ケアマネ)
- 病院・施設・在宅リハなど幅広く経験
- 専門学校で理学療法士養成に従事
- 延べ500人以上の学生の就職相談にのる
- 適応障害(うつ状態)をきっかけに働き方を見直す
- 心身の健康管理、ストレス対策について専門的な視点で深く学び直す
- 理学療法士の視点から、コンテンツを発信中
ストレス①:人間関係の摩擦

理学療法士の現場は、多職種連携が基本です。
医師、看護師、作業療法士、言語聴覚士、介護士、ケアマネジャーなど、多様な職種と関わりながら患者様のケアを行います。
ここでしばしば起こるのが「認識のズレ」や「役割の押し付け」による摩擦です。
また、職場内の上下関係や派閥のような人間関係にも悩まされがちです。
新人や中堅時代は特に、自分の意見を主張しにくく、ストレスを溜め込みやすい傾向があります。
- 職種ごとの立場や役割を理解した上で、敬意ある伝え方を意識する
- 過度な共感でなく、“共存”のスタンスを取る
- 職場外に相談できる仲間(同職種・他施設)を持つこと
ストレス②:過重労働と時間管理

患者対応や書類業務、カンファレンスなど、理学療法士の業務は多岐にわたります。
特にスタッフが少ない施設では、担当患者数が多く、昼休みも返上して働くことが常態化しているケースもあります。
「タイムスケジュールに追われて、自分のやりたいケアができない」といったジレンマは、やりがいのある仕事であればあるほど強くなります。
- 業務の優先順位を明確にし、“やらないこと”を決める勇気も持つ
- 業務時間内に完了できる仕組みづくり(テンプレートの活用など)
- 管理職と業務量について定期的に相談する
ストレス③:評価制度・昇給の限界

「毎日一生懸命やっても、評価は年功序列」「昇給はわずか数千円」—こうした声をよく聞きます。
医療・介護業界全体に言えることですが、特に理学療法士の昇進などのキャリアパスは限られています。
評価されないことによるモチベーションの低下や、将来への不安がストレスの大きな要因になります。
- 副業や資格取得など、自分のキャリアの選択肢を広げる行動をとる
- 組織内でのポジションに依存せず「自分の市場価値」を意識する
- キャリアコンサルタントや転職エージェントに相談して情報を得る
 しんた
しんた私も以前、“頑張っても評価されない…”という閉塞感に悩んでいました。でも、転職エージェントに相談して初めて、今の職場以外にも自分の価値を認めてくれる場所があると気づけたのです。選択肢を知ることは、心の余裕につながります。
ストレス④:感情の共感疲労(共感疲労)


リハビリテーションを通じて患者様と長く関わる中で、相手の感情や苦しみに深く共感してしまい、心が疲弊する「共感疲労」に陥ることがあります。
とくに真面目で優しい性格の理学療法士ほど、この影響を受けやすい傾向があります。
- 感情に巻き込まれすぎない“心理的距離感”を意識する
- 定期的に振り返りの時間(リフレクション)を取り、自分の感情を客観視する
- 趣味や運動など、仕事以外に心を回復させる手段を確保する
ストレス⑤:成長実感の停滞とマンネリ
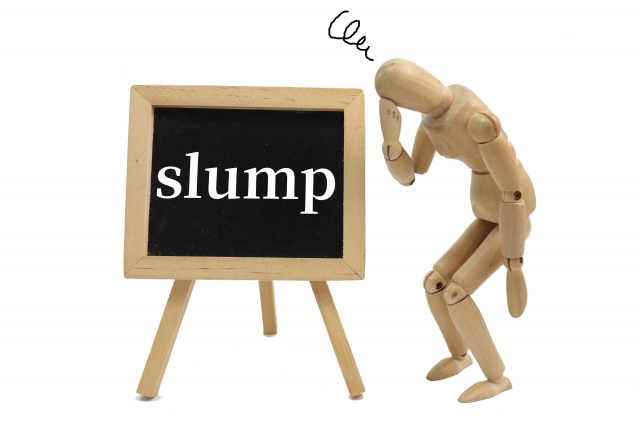
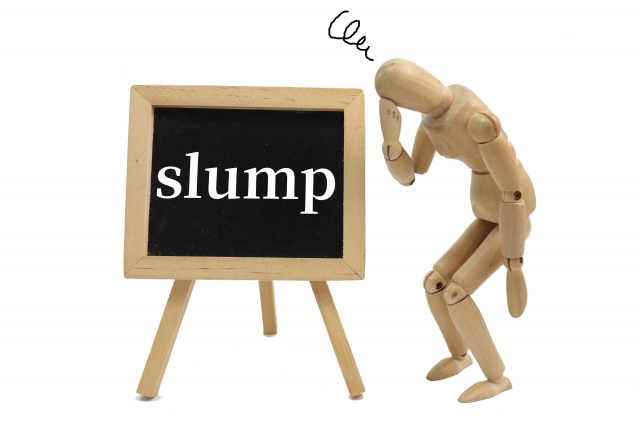
臨床経験が5年、10年と積み重なると、「自分はこれ以上何を学べばよいのか?」「ルーティン化して刺激がない」と感じることがあります。
これもまた、静かなストレスの一種です。
- 学会や勉強会の参加で新しい刺激を得る
- 他施設への転職や部署内の異動(ローテーション)で環境を変える
- 新人教育や後進指導など、新たな役割を持つことで視点を変える
まとめ


ストレスは避けるべきものではなく、「自分の働き方を見直すサイン」でもあります。
この記事で紹介した5つのストレスは、多くの理学療法士が一度は経験するものです。
大切なのは、「自分の心と身体の声に気づくこと」、そして「一人で抱え込まないこと」。
ストレスと上手に付き合いながら、無理なく、自分らしく働く道を探していきましょう。
転職やキャリアの相談も、選択肢のひとつです。
必要なら、専門のエージェントやカウンセラーに話を聞いてもらうことをおすすめします。