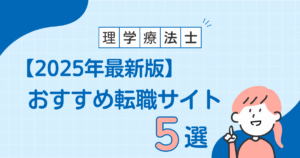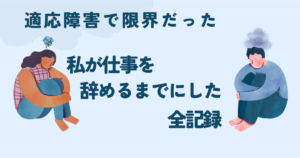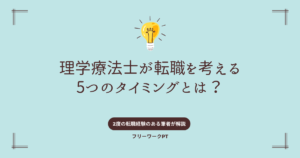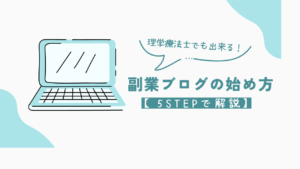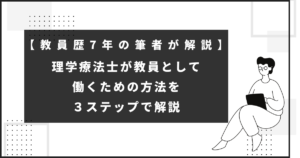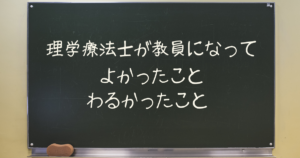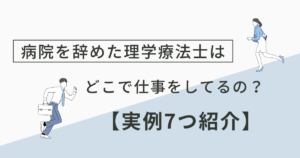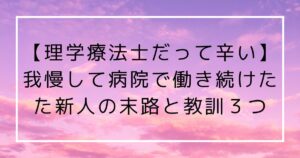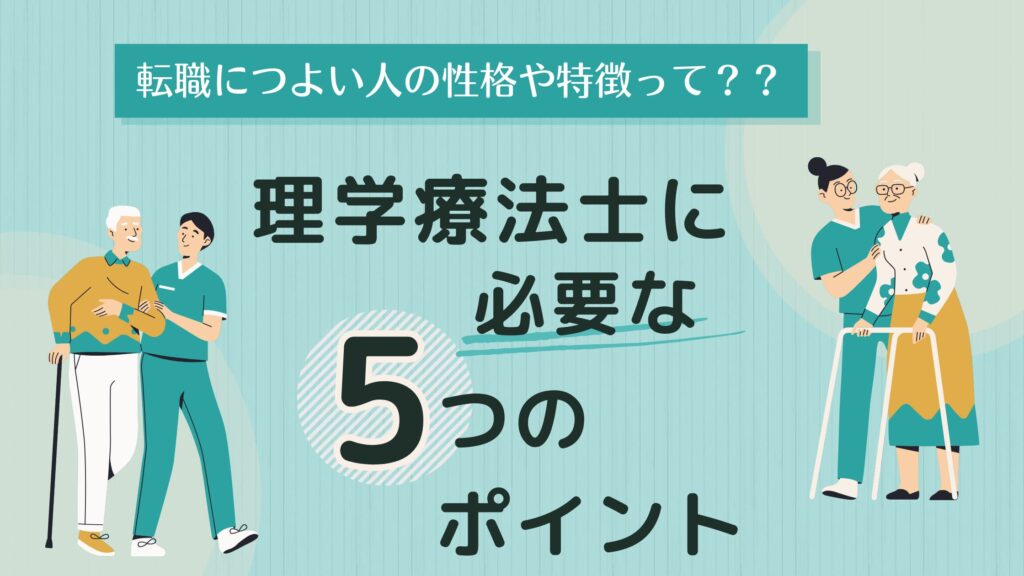

今の職場にずっといていいのかな…



転職したいけど、どこならうまくいくんだろう?
理学療法士という専門職は、一見すると“安定した職種”に見えるかもしれません。
しかし実際には、働く現場によって忙しさや人間関係、やりがい、待遇に大きな差があり、転職を考える理学療法士は年々増加傾向にあります。
一方で、同じような経験年数・スキルを持っていても、すぐに内定を得る人と、なかなか決まらない人がいるのも現実です。
では、何がその差を生むのか?
教育現場で多くの学生や若手PTと向き合ってきた筆者が、「転職に強い理学療法士」にはどんな共通点があるのかがわかりました。
そこで、“キャリアが伸びる人”と“停滞してしまう人”の分かれ道を徹底解説します。
・自分の働き方に悩んでいる方
・転職を視野に入れつつも動けずにいる方
・キャリアを戦略的に築いていきたい方
そんな方にこそ読んでいただきたい記事です。


- 資格:理学療法士(PT)、介護支援専門員(ケアマネ)
- 病院・施設・在宅リハなど幅広く経験
- 専門学校で理学療法士養成に従事
- 適応障害をきっかけに働き方を見直す
- 得意分野:心身の健康管理、姿勢改善、ストレス対策
- 理学療法士の視点から、ブログ・書籍・デジタルコンテンツを発信中
- 家族:妻・子ども2人の父親
1、転職に強い人の5つの特徴


1-1. 主体的に学び続けている
医療・介護の分野は、最新の知見や技術が常にアップデートされるため、“学ばない人”はすぐに時代遅れになります。
私が教育機関で指導していた学生の中にも、卒業後に定期的に学会に参加したり、後輩に勉強会を開いている卒業生がいます。彼らは臨床経験3〜4年目で「リーダー」として昇進したり、外での活躍が評価され、他施設から声を掛けられて、転職することもありました。
学びは“将来の自分の市場価値”を高めてくれます。
1-2. コミュニケーション能力が高い
チーム医療・多職種連携の現場では、知識よりも「伝え方」「関わり方」が問われる場面も多いです。
ある学生が、臨床実習中にとても印象的だったのは、患者様や職員の方と信頼関係を築くスピードでした。技術的にはまだ未熟でしたが、患者様が笑顔で施術を受ける姿を見て、指導者から「この子は伸びる」と高評価。実際にその子は卒業後、就職先でも高評価を得ており、後の転職もスムーズでした。
1-3. 自分の“得意分野”を言語化できる
面接や履歴書では、「できることを具体的に説明できる人」が採用されやすい傾向です。
筆者が病院で働いていたとき、採用面接に同席した際に、同じような経験年数の応募者2人のうち、「〇〇疾患にや、△△分野について強い関心がある。□□の学会などにも参加している」と、自分のことを具体的に話した方が採用されました。
逆に「患者様と関わるのが好きです」といった抽象的な回答では、面接官にも伝わりにくいのが現実で、転職の機会を損なうことになります。
1-4. 臨床以外の経験がある
転職市場では「+αのスキル」を持つ人が重宝されます。
ある後輩は、通常の臨床業務のかたわらで、院内の研修会企画や、地域向けの健康教室を担当していました。履歴書にその実績を記載したことで、教育系施設に転職する際に「即戦力」として評価され、実質書類選考で内定が決まりました。
こうした“サブスキル”を明確にしておくことは、将来的にも有利になります。
1-5. キャリアの方向性が明確
転職理由に一貫性がある人は、採用側から「長く働いてくれそう」と思われる。
かつて、臨床経験3年目で「教育に進みたい」と相談に来た卒業生がいました。
彼は明確に「自分が苦労した経験を、次の世代に伝えたい」と語っており、その熱意が伝わり、教育系施設の採用がスムーズに進みました。
「なんとなく転職したい」という曖昧な動機は、面接官にも伝わり、転職活動も難航してしまいます。
2. 教育現場でわかったキャリアの“分かれ道”


2-1. 与えられるのを待つ人 vs 自ら動く人
自分から動く人は、“チャンスを待たずに取りに行く力”がある。
養成校の教員時代、ある学生Aさんは、課題や実習を“最低限こなす”タイプ。
一方で、学生Bさんは授業後に質問しに来たり、参考書を“自主的に”読み進めていました。
卒業後、Aさんは「仕事が合わない」と悩んで転職を繰り返しましたが、Bさんは「院内勉強会を任される立場になった」と報告をくれました。
この差は、在学中からの“姿勢”にすでに現れていたのです。
2-2. 「とりあえず3年」の落とし穴
「続けること」そのものが目的になると、成長が止まる。
昔から「3年は辞めないほうがいい」という言葉がりますが、その言葉を信じて働いていた卒業生がいました。
しかし、後に今の病院を転職したいと相談があり、話を聞くと「何も考えず、ただ出勤して、帰るだけの日々でした」と振り返っていたのが印象的でした。
一方で、1年目から「学びたい分野」「理想の働き方」を明確にしていた学生は、2年目にはスキルも信頼も得ており、上司からの推薦で外部研修にも参加し、その実績もあり、転職もスムーズでした。
大事なのは“年数”ではなく“濃度”です。
2-3. “情報感度”の差がキャリアを分ける
良質な選択は、“知っている人”しかできない。
ある卒業生が、早くから訪問リハビリに興味を持ち、学会やSNSで現場の声を収集していました。結果、卒後1年半で訪問に転職し、今では講師として地域セミナーにも登壇しています。
逆に、病院しか選択肢がないと思い込んでいた学生は、「自分が何をしたいかわからない」と迷っていました。
キャリアは、“情報収集力の差”で未来が変わり、またその速度にも大きく差がでるのです。
3. 教員経験から見えた学生と若手PTのキャリア観の変化


3-1. 「一生病院勤務」思考が減ってきている
医療の多様化により、「臨床=病院」ではなくなってきている。
10年前は「病院で働きたい」という学生が大半でした。
しかし、近年は「起業してセルフケア動画を発信したい」「保険外サービスで自由な働き方がしたい」と話す学生が増えています。
実際、卒業後すぐにSNSでの発信を始め、整体院と業務提携しながらフリーランスPTとして働き出した卒業生もいます。
いまや、「病院に勤めて一人前」という時代ではなくなりつつあります。
3-2. ワークライフバランス重視の傾向
医療職の「やりがい」だけでは、働き続けるには限界があると実感している人が多い。
ある学生は、「先輩が疲弊して辞めていくのを見て、違う働き方を考えたい」と在学中から話していました。
結果、彼女は週4日勤務の訪問リハ施設に就職し、残りの1日は家族との時間や資格取得の学習に充てています。
「自分を犠牲にする働き方」から、「自分を大事にする働き方」へと意識が変わってきていると感じます。
3-3. 情報収集力がそのまま“キャリア力”に
知識・現場の情報・求人情報に早く触れることで、選択肢と自信が増える。
情報収集が得意な学生は、在学中から理学療法士の実際の働き方を調べ、実習前から「私はこの分野を目指したい」と明言していました。
一方、受け身で情報を待つだけの学生は、卒業直前でも「どんな就職先があるのか、よくわからない」と不安そうで、実際なかなか就職先は決まらず苦労していました。
この差は、卒業後のキャリアの勢いにもはっきりと表れています。
4. 転職で後悔しないために今からできること


4-1. 自分の棚卸し
「どんな働き方がしたいか」「自分の強みは何か」を言語化できないと、転職先の選定基準もブレやすくなる。
ある後輩PTが「やりたいことが分からない」と相談に来た際、私は「これまで楽しかった瞬間と、嫌だったことを書き出してごらん」とアドバイスしました。
すると彼は、「急性期のスピード感は自分に合わない」「患者とじっくり関わるほうが好き」と気づき、結果として回復期病院への転職が大成功に。
“内省する力”は、キャリアを決める羅針盤になります。
4-2. 転職サイト登録で“市場”を知る
求人情報を知らずして、理想の職場は見つかりません。登録は「行動の第一歩」です。
ある卒業生が「今の職場がなんとなく合わない」と相談してきましたが、話を聞くと“転職サイトを一度も見たことがない”状態でした。
登録してみると、「意外と時短勤務や在宅併用できる求人もあるんですね」と驚いていました。行動すれば視野が広がり、安心感も得られます。
▶ おすすめサイト
4-3. 学び続ける姿勢を“見える形”にする
「成長意欲」は評価されやすいが、伝わらなければ意味がない。
私が非常勤で関わっていた教育現場に、講師として招いた卒業生がいました。彼は在学中から研修報告や資料作成をSNSで公開しており、それを見た現場の上司が「人に教える力がある」と評価して推薦してくれたそうです。
こうした“外から見える実績”は、履歴書以上にあなたの価値を証明してくれます。
まとめ|“転職に強い理学療法士”になるには?


理学療法士としてキャリアを築いていく中で、「今の職場でこのまま働き続けていいのか?」と立ち止まる瞬間は誰にでもあります。
教育現場で多くの学生や若手PTと向き合ってきた経験から、“転職に強い人”には共通する姿勢や行動習慣があることが分かってきました。
その特徴を振り返ると──
- 自ら学び、行動する力
- 得意を言語化する力
- 情報収集力
- 他人任せにしない主体性
- キャリアの方向性を描く力
こうした力は、突然備わるものではなく、日々の意識と行動の積み重ねで育まれるものです。
今の職場に違和感があるなら、まずは自分のキャリアや経験の棚卸しから始めてみてください。
そして、行動の第一歩として、転職サイトなどで、どんな選択肢があるのかを知ることも大きな一歩です。
💡今すぐできる“第一歩”
- 自分の強み・苦手・希望条件を紙に書き出す
- 転職サイトに登録して、非公開求人や条件をチェック
- 研修・発信・SNSなど、学びを自分にも“見える形”にする
✅「転職=逃げ」ではなく、「自分らしい働き方を選ぶための行動」です。